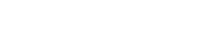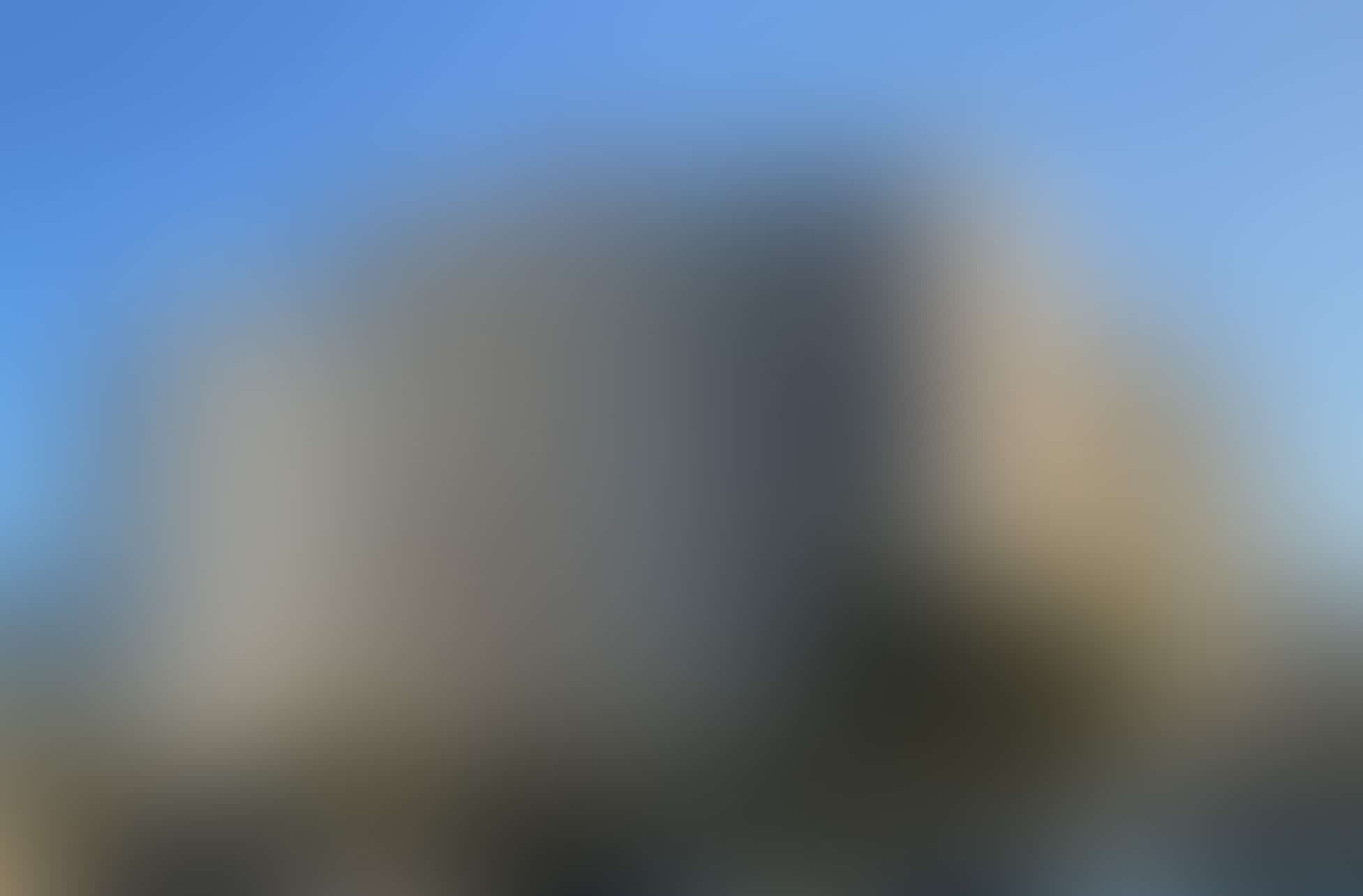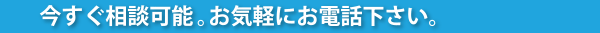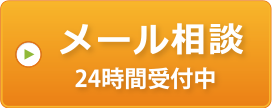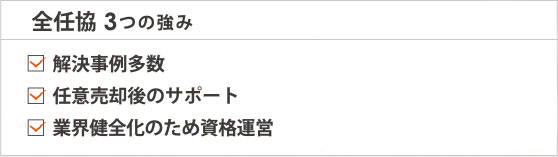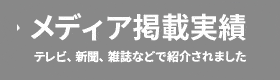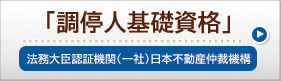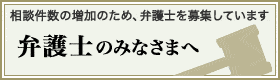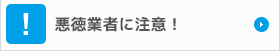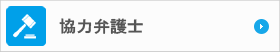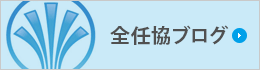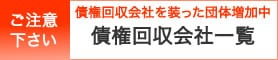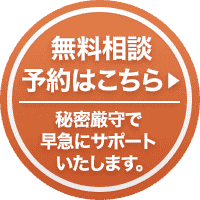任意売却とは
任意売却とは、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンの返済が厳しくなった際、住宅を売却し住宅ローンの返済にあてるという選択肢がございます。
一般的に所有する不動産を売却する場合、もしその不動産に抵当権が設定されているのであれば、売却時に金融機関などの債権者へ借入金を全額返済し、抵当権を解除してもらわなければなりません。
しかし、売却金額で住宅ローンを全額返済できない場合や、返済のための不足分を自己資金で補えなえない場合もございます。その際に、抵当権の抹消を金融機関に応諾してもらい売却することを任意売却と言います。
任意売却については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
任意売却とは?競売でお困りの方にプロがわかりやすく解説!
任意売却には債権者の同意が必要
任意売却を行う際、金融機関などの債権者の同意が必要になります。
同意が得られないと任意売却を行うことができず、競売にかけられ売却されてしまします。
ではなぜ債権者の同意が必要になるのか解説します。
なぜ同意が必要なのか?
競売を避けるために任意売却を進めるにあたり、様々な手続きが必要となります。
そのなかの1つとして、抵当権の抹消がございます。
住宅は抵当権が抹消できなければ売却ができない場合が多いです。
抵当権がついたまま購入する場合、購入者にとってリスクが大きく、多くの場合抵当権がついた住宅を購入することはないためです。
住宅ローンを計画通り返済し、完済できた場合は銀行などの金融機関から抵当権の解除手続きに必要な書類一式が送られてきます。
しかし、住宅ローンの完済ができない上で、抵当権を抹消するためには、金融機関などの債権者の同意が必要となります。
そのため、任意売却を行うには債権者の同意が必要となってくるのです。
そもそも抵当権とは
任意売却を行う上で、抵当権を抹消する必要性はわかったかと思いますが、そもそも抵当権とは何かを説明します。
抵当権とは、金融機関などの債権者が、お金を借りている債務者に対して住宅ローンなどの融資を行う際に、債務者が購入する不動産を担保として登記する権利のことをさします。
複数の金融機関からお金を借りている場合、債権者は複数存在し、同様に抵当権も複数存在する可能性があります。
ローンの返済を約束通り行っていれば、抵当権が行使されることはありません。
しかし、債務者が住宅ローンの返済を一定期間以上怠った場合、債権者は抵当権を行使することができます。
抵当権が行使されると、担保となっている不動産が差押えられ、強制的に競売に出されてしまいます。債権者は競売で売却した代金から優先的に債権の回収ができます。
またこの際、返済しきれなかった住宅ローンは残債としてのこり、債務者は返済を継続していく必要があります。
債権者は同意してくれるか?
債権者の目的は債権の回収です。
市場価格の2~3割低い価格になる可能性がある競売に比べ、任意売却では市場価格により近い価格で売却することができます。
そのため、債権者にとっては任意売却の方が住宅ローンをより多く回収できる可能性があるため任意売却を行うメリットが大きくなり、応じてくれる可能性は高いです。
しかし債権者が複数いる場合は同意が得られない可能性もあります。
債権者が複数いる場合どうなるか、解説していきます。
債権者が複数いる場合
抵当権を有する債権者が複数いる場合は、任意売却に応じてもらえない場合もあります。
物件を売却した代金の配当は抵当権を登記した順に配当されていきます。
抵当権を2番目以降に設定した抵当権者は後順位抵当権者と呼ばれ、第1抵当者の回収が完了し、残った分を受け取ることができます。
そのため、住宅ローンを返済できない場合に住宅の売却を行う大半のケースでは、第1抵当者のみが実際に債権を回収できる事が多く、後順位抵当権者である2番目、3番目以降の債権者は、売却代金からは配当が少なくなる可能性があります。
例えば第1抵当者が1000万、第2抵当者が500万、第3抵当者が300万円をそれぞれ設定していた場合、仮に住宅の売却代金が900万円である場合、第1抵当者のみが900万円を回収できることとなり、後順位抵当権者はお金がもらえなくなってしまいます。
そのため、任意売却では後順位抵当権者の協力を得て抵当権の抹消を行うために、担保解除料(ハンコ代)を支払い抵当権の抹消をお願いする必要あります。
売却金額が低い場合はハンコ代が必要
抵当権の抹消を行うために、配当が見込めない後順位抵当権者に対して、抵当権抹消に対する協力金として配当する費用を担保解除料(ハンコ代)といいます。
法律上、第1抵当者は後順位抵当権者にハンコ代を払う義務はありません。
しかし、後順位抵当権者の協力を得て抵当権の抹消を行わないと任意売却を行うことができません。
そのため、売却金額が低く、第1低当者の融資額 「債権額」変更 よりも低い場合、任意売却を実行するには、第1低当権者にお願いをし、第2抵当権者、第3抵当権者に担保解除料や担保抹消料(ハンコ代)を払う許可を頂く必要があります。
また、差押や仮処分といった担保設定の抹消や取り下げに協力してもらうようにお願いする場合や、他の債務における差押がなされている場合はより一層の調整力が求められます。
ハンコ代はいくら払うという決まった規定があるわけではありません。債権者との相談によりいくら払うかは決めていきます。
フラット35などの住宅ローンを提供する住宅金融支援機構では、後順位抵当権者に渡すハンコ代として以下の様な基準を設けています。
| 第2順位 |
(1)30万円 (2)残元金の1割 |
| 第3順位 |
(1)20万円 (2)残元金の1割 |
| 第4順位以下 |
(1)10万円 (2)残元金の1割 |
注意事項として、ハンコ代は(1)または(2)いずれかの低い方の額となります。支店によっても扱いが異なりますので、住宅金融支援機構の債権回収窓口をご確認ください。
豊富なネットワークを持つ業者に頼むことが大事
任意売却は普通の不動産取引とはことなり、専門知識が多く必要になってきます。
そのため通常の不動産ではなく、専門の業者に頼むことが大事になってきます。
当協会では長年のネットワークやコネクションがある為、任意売却を専門で行う他社で合意が取れなかった方でも、合意を得られた実績が多数御座います。
ご連絡先は、フリーダイヤルへお電話下さい。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
このページの先頭へ▲
競売回避した解決事例
当協会が行った解決事例の一部をご紹介します。
競売開始決定通知書を受け取ってから解決した事例
-
相談内容:
神奈川県川崎市、15年ほど前にお父様がお亡くなりになり、そちらに関して相続手続きを放置していたそうです。父の死後(お母様はお父様より先に亡くなられ…詳細の解決事例
-
相談内容:
独身時代に購入した目黒区にあるワンルームマンションを、結婚をきっかけに賃貸してました。結婚して専業主婦になりご主人の収入のみの生活になりました。家…詳細の解決事例
-
相談内容:
豊島区のMさんは、独身の時にワンルームマンションを購入し、住んでおりました。ご結婚をし、そのワンルームマンションを収益物件として管理してました。御…詳細の解決事例
競売の期間入札通知書を受け取ってから任意売却で解決した事例
-
相談内容:
息子様からのご相談でした。お父様の心臓に病気が見つかり、入院しICU等に入っている期間も含め、住宅ローンの支払いができなくなり、退院した時には競売…詳細の解決事例
-
相談内容:
離婚を機に関東で再就職された相談者のNさん。再就職は無事に決まったものの、以前に比べて収入が減ってしまいました。養育費の支払いなどを最優先にさせて…詳細の解決事例
-
相談内容:
東京都世田谷区で製造業を営むKさん。リーマンショック以降、受注が激減し、経営が低迷。自宅を担保に借りた運転資金の返済が滞り、督促状や催告書が届くよ…詳細の解決事例
その他の解決事例
このページの先頭へ▲
関連コンテンツ

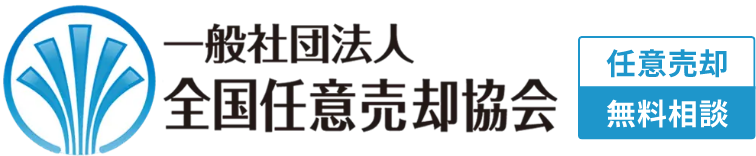
 LINE相談
LINE相談
 メール相談
メール相談
 無料相談予約
無料相談予約