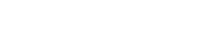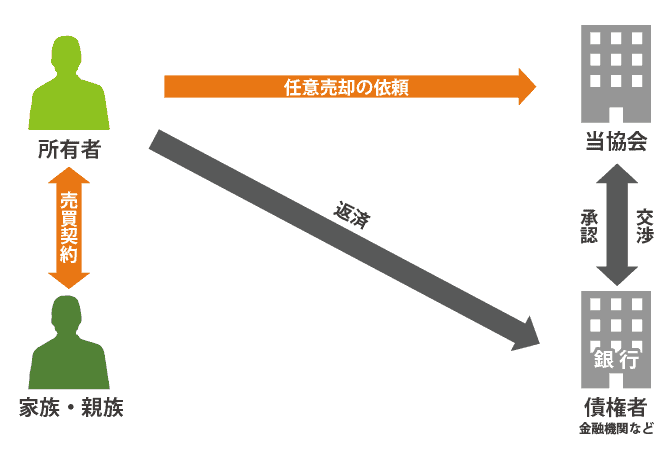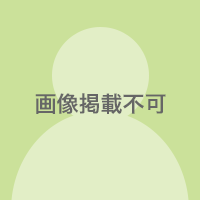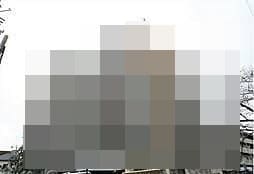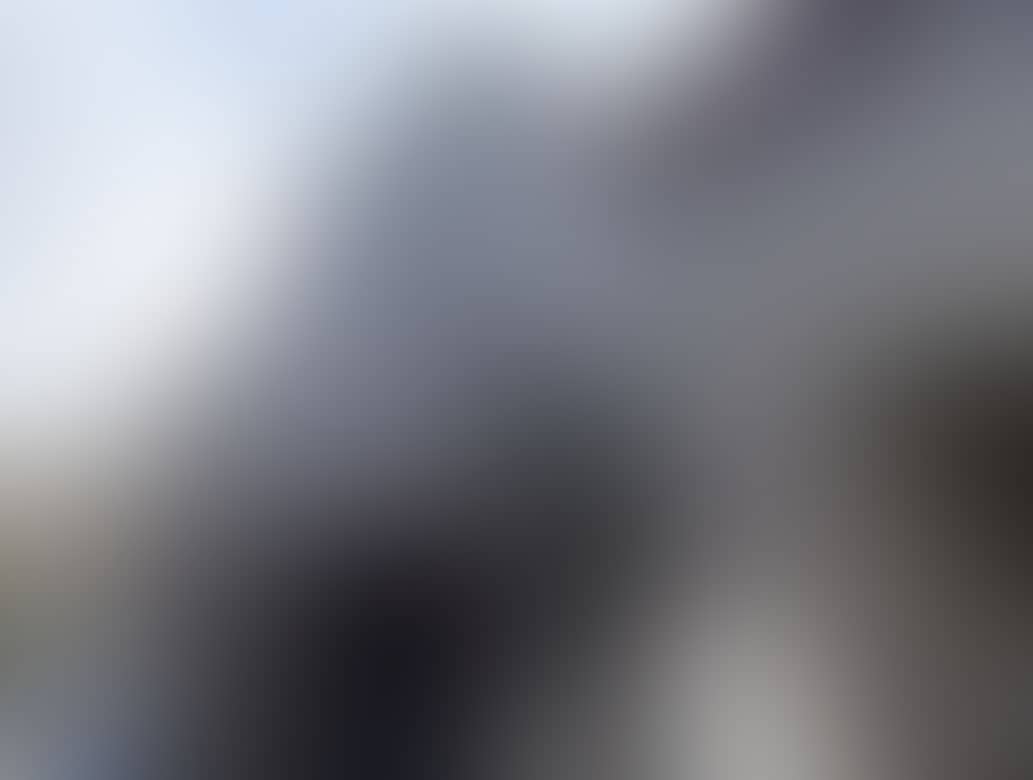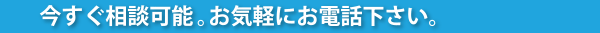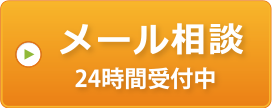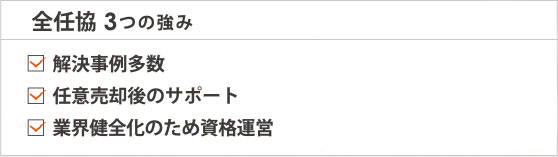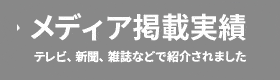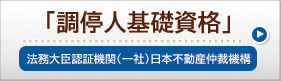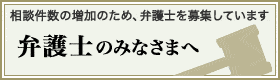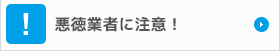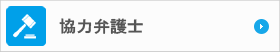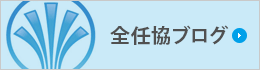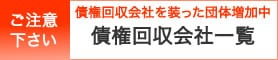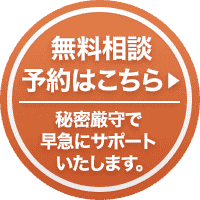掲載日:2023年9月28日 最終更新日: 2025年4月13日
親子間売買とは?
親子間売買とは、その名の通り、親子間で不動産(主に自宅)を売買することです。
親子間売買後に、そのまま元の所有者が不動産を使い続けることから、セール(売却)&リースバック(借り戻し)とも言います。
親子間売買の相関図
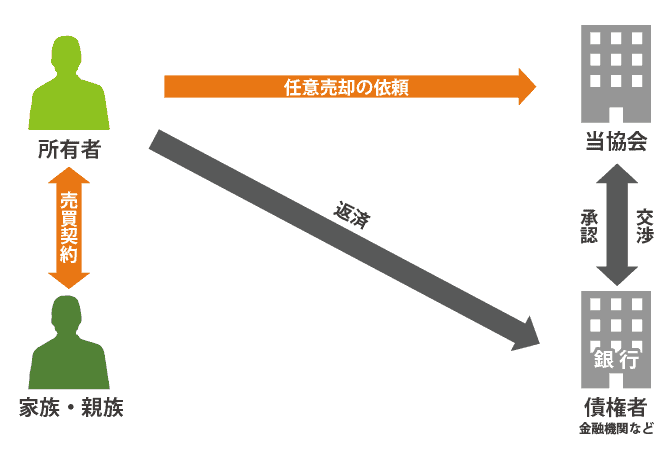
このように親子間で通常の不動産と同様に売買契約を結ぶのが親子間売買になります。
また親子間だけでなく、兄弟間や親戚間での売買を行う親族間売買もあります。
親族間売買での「親族」範囲
親子間売買では親と子という関係があり明確でわかりやすいですが、親族となるとどこまでの範囲になるのでしょうか?
実は不動産において、親族間売買での親族の範囲は明確に定められていません。
民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定められています。一方、税務署では「みなし贈与」が発生しているかどうかが重要になり、相続人に該当する親族がその範囲と考えられています。
そのため民法上の範囲外であっても親族間売買にあたると注意することが必要です。
「みなし贈与」については下記で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
親族間売買はみなし贈与になる?注意点と成功事例をプロが解説
親子間売買で自宅に住み続けられる?

ご自宅の住宅ローン滞納で任意売却のご相談に来られる多くの方は「自宅に住み続けたい!」と強く希望されます。
愛着のあるご自宅を手放したくない、子供を転校させたくない、自宅の近所に介護している両親が住んでいる、自宅兼店舗のため店を閉めたくない、など、自宅に住み続けたい理由は様々です。
競売の場合、購入者には引渡命令という制度が用意されており、前所有者の立退きを比較的簡単に強制執行することができます。
そのため、競売になってしまった場合、ご自宅に住み続けることはほぼ不可能ですし、買戻すことも難しい、また立退き料がもらえる可能性は非常に低くなっています。
しかし、ご自宅を息子さんや娘さんなど子供に売却する「親子間売買」という形で任意売却をすれば、ご自宅を売却した後もご自宅に住み続けることができます。
子供が所有者となり、形式上、親がご自宅を賃貸するというものです。
全任協のホームページでは親子間売買で自宅に住み続けられた方の実例紹介をしております。
子供以外の親族などの身内が購入する場合は「親族間売買」、夫婦間で行う場合は「夫婦間売買」、親族以外が購入する場合を「リースバック」と呼ぶこともあります。
リースバックとは正式には「セル&リースバック」といい、売却した資産(自宅)を賃貸して使用し続ける不動産取引全般を指すものです。
リースバックについては、下記の記事で詳しく紹介しています。
リースバックと任意売却で自宅に住み続ける
親子間売買のメリット・デメリット
親子間売買の最大のメリットは、任意売却後も自宅に住み続けられることです。
ただ、デメリットも存在します。検討する前に、そのメリットとデメリットをよく理解するようにしましょう。
親子間売買のメリット
- 1.思い出や思い入れの詰まった自宅に住み続けることができる
- 2.引越をしないで済む(引越しの手間や費用がかかりません)
- 3.毎月の返済負担が少なくなるケースが多い
- 4.親子間、親族間での取引のため、外部に経済状況を知られる恐れがない
親子間売買のデメリット
- 1.融資してくれる金融機関が少ない
- 2.親の自宅を買い取った子供が、自分の家の住宅ローンが組みづらくなる)
- 3.親子間トラブルを巡る詐欺などトラブルが多い
親子間売買は難しい?
親子間売買のほとんどのケースでは、購入する子供が新たに住宅ローンを組む必要があります。
しかし、ほとんどの金融機関は、親子間での売買や兄弟姉妹間の売買に対して融資をしません。
これは、悪用しようとすれば、融資したお金が別のことに使われる可能性があり、また、不当に安く(高く)売買されてしまう可能性もあるためです。
ですが、親子間売買や親族間売買(特に兄弟姉妹間売買)に対して住宅ローンを提供する金融機関は少数ですがあります。
当協会では親子間売買の成功事例が多くあり、どうすれば親子間売買を成功させることができるかというノウハウを持っています。
親子間売買での住宅ローンは一般的な住宅ローンに必要な条件(十分な年収や持病などがないこと)を満たせば借りることは可能です。
自分は可能か、税金はどうなるのか、など気になる点はフリーダイヤル(0120-963-281)かメールフォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。
当協会であれば、親子売買ローンで優遇が適用されます。
全任協は親子間売買ローンに関し、セゾンファンデックスと提携しています。
全任協を窓口としたセゾンファンデックスの親子間売買ローンでは、通常のローン利用に対して年利マイナス0.2%の優遇が適用になります。
対応エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、名古屋市、福岡市の全域、京都府、奈良県、滋賀県、茨城県の一部です。
「親子間売買ローン」をご希望の場合は、是非お気軽にフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)までお電話ください。
協会への電話相談は年中無休、全国対応で9:00~20:00とさせて頂いています。
無料相談フォーム、または公式LINEアカウントでのご相談は24時間可能ですので、いつでもご都合のよい時にお送り下さい。
※親子間売買のご相談は日本全国より受け付けております。
親子間売買で住宅ローン控除を適用できるのか
親子間で住居の売買をするとき、「住宅ローン控除」を適用できるのかも知っておきましょう。
住宅ローン控除について簡単に
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住居を購入・建築する際に適用される所得税控除特例です。
最大4,000万円までの住宅ローン借り入れに適用され、最長13年間にわたって基本的に「年末時点の住宅ローン残高の1%」の税額が控除されます。
なお住宅ローン控除制度はもともと「最長10年間」でしたが、消費税増税時期に合わせて「最長13年間」まで延長されています。
それにともない、11~13年目までの控除率は上記と異なる割合が適用される可能性があります。
たとえば年末時点で4,000万円の借入残高があって1%の控除を10年間受け続ければ、それだけで400万円分の税金控除を受けられます。
会社員でも自営業者でも利用できるので、節税対策に大きな効果を発揮するでしょう。
親子間売買の場合、住宅ローン控除を適用できない?
親子間売買の場合、「住宅ローン控除を利用できない」と思われている傾向がありますが、そういった規制はありません。
親子間売買でも条件さえ満たせば住宅ローン控除が適用されます。
ただし住宅ローン控除は「売主と買主の生計が同一の場合」には適用されません。
同居の親子や生活費の仕送りをしている親子が売買すると、住宅ローン控除を利用できないので要注意です。
また住宅ローン控除を適用するには、当然「住宅ローンの利用が必須」です。
親子間売買の場合、金融機関が住宅ローン審査に通さない事例が多いので、そもそも住宅ローンを利用できない可能性も高くなります。
こういった事情があって「親子間売買の場合、住宅ローン控除のハードルが上がる」ため、一般に「親子間売買の場合には住宅ローン控除を適用できない」と思われている現状があります。
しかし「親子が別々に暮らしていて生計が別」であり、かつ「きちんと金融機関で住宅ローン審査にとおり住宅ローンを組んだ」場合には、一般的な案件と同様に住宅ローン控除を適用できます。
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除の適用要件を簡単にまとめると、以下の通りです。
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上
- ・住宅の床面積が50平方メートル以上
- ・一定の耐震基準を満たしている
- ・実際に家に居住している
- ・買い主と売り主の生計が別
- ・買い主の年収は3,000万円以下
親子間売買の場合、一般的に住宅ローンの借入額が少額となって返済期間も短くなりがちです。
しかし返済期間が10年を切ってしまうと住宅ローン控除の適用外となるので注意して下さい。
また住宅が古い場合などには耐震基準の問題が発生する可能性もあります。
親子間売買で住宅ローン控除を受けるためにすべきこと
住宅ローン控除を受けるには、金融機関で住宅ローン審査に通ることが必須です。
自分たちだけで金融機関に相談にいくとローン審査に落とされる可能性が高まるため、当協会のような専門業者に協力を求め売買が公正かつ正当なものであることを証明するようお勧めします。
また専門知識を持っている業者に相談したら、対象住宅や住宅ローン契約の内容が住宅ローン控除の適用条件を満たしているかも確認できます。
親子間売買をお考えであれば、是非とも経験と知識の豊富な当協会へご相談下さい。
親子間売買の注意点
最近ではインターネット等で調べ、親子間売買を知ってむやみやたらに、銀行や信用金庫に申し込まれてる方がいるようですが、ほぼ100%の確率で断られてしまいます。
難易度の高い売買の方法ですので、一般の方がネット知識ぐらいで成就するほど、簡単で安易な取引ではありません。
それどころか、一度でも申込を断られますと、断られた履歴が個人情報として半年間残ってしまうので、任意売却を取り扱っている金融機関に申込んでも、その履歴によって否決されてしまう事が多々あります。
もし、親子間売買に代表される親族での売買をお考えの方は、自分で既入金に相談したり、融資の申込をする事は、絶対に止めて、協会のような専門家に依頼してください。
親子間売買は難しいが、自宅に住み続けたいときはどうする?
当協会にご相談いただくケースの中には、今は子供が住宅ローンを組めないが、数年後には住宅ローンを組める可能性が高いケースがあります(例えば子供が就職・転職したばかりという場合)。
また、住宅ローンの滞納が続き、競売が開始されているようなケースでは時間がなく、親族間売買の調整が間に合わない場合もあります。
その場合、一旦投資家に自宅などの不動産を売却し、数年後に買戻しをするというリースバックを行うという手段もあります。
その間、買戻しをしてくれる親族を探すこともできます。
リースバック&買戻しが成功するかどうかは、ご相談者さまとご自宅を購入した方が、お互い信頼し合える関係かどうかにかかっています。
近年リースバックにおけるトラブルも多く発生してきているため、信頼できる投資家かどうかの観点は非常に重要になります。
当協会では、ご相談者さまの事情や状況に合わせ、任意売却やリースバックの経験がある、信頼できる投資家のご紹介もしております。
リースバックについては「リースバックと任意売却」のページで詳しく紹介しています。
親子間売買と贈与税について
親子間で住宅売買をすると「贈与税」が課税される可能性があるので注意が必要です。
「売買なのに、なぜ贈与税がかかるのか?」と疑問を持たれるかもしれませんが、以下2つの場合に当てはまる場合は課税されます。
- ①相場より不当に安い価格で取引をするパターン
- ②売買契約書を作成しないパターン
課税される理由をそれぞれみていきましょう。
①相場より不当に安い価格で取引をするパターン
1つには「相場よりも不当に安い価格で売買するから」です。
親子間の場合、一般取引のような厳格な対応をする方は少数です。きちんと価格査定しない方も多く「相手の負担にならないように」という気持ちから通常より安い価格設定や破格な安値を設定してしまう方も少なくありません。
しかし通常より安い価格で売却すると「減額した部分を贈与した」のと同じになってしまいます。
たとえば3,000万円の価値のある住宅を500万円で売買したら、売主が買主へ2,500万円の贈与を行ったのと同じになり、後に税務署が調査に入ったとき、2,500万円分に贈与税を課税されてしまいます。
このように「売買」であっても「贈与とみなして課税される贈与税」を「みなし贈与税」といいます。親子間売買で安易な対応をすると、予想外に高額な「みなし贈与税」がかかってしまう危険性が高まるので要注意です。きちんと不動産の「適正価格」を調べてあてはめ、取引を進めましょう。
適正価格を知るには専門業者の協力が必要
素人の方が自力で不動産の適正価格を調べるのは困難です。私たち全国住宅ローン任意売却支援協会のような、プロに査定を依頼して相場を反映した適正な価格を把握しましょう。この意味でも任意売却における親子間売買を成功させるには、ノウハウをもった専門業者に依頼することが大切です。
②売買契約書を作成しないパターン
親子間売買の場合、きちんと売買契約書を作成しない事例が多数あります。「お互いにわかっているし、契約書を作成するなんて大げさだ」ということで、口約束で済ませてしまいがちです。
しかしそのようなことをすると、後に税務署が調査に入ったときに「売買による所有権の移転です」と主張しても証明できません。特に現金手渡しで決済していると、預貯金取引履歴などでも資金の移動が確認できないので売買を否認されやすくなります。「売買でない」ということになると、評価額全額に対する贈与税がかかります。
親子間売買であっても必ず売買契約書を作成しなければなりません。自分たちで作成したものでは不安があるので、私たちのようなプロにお任せ下さい。当協会では親子間売買における贈与税課税対策についての対応も万全です。
親子間売買のQ&A
- Q. 親子間売買ってどういう場合にできるの?
- A. 親子間売買は資金(住宅ローン)の手当てが重要です。また、子供が既に住宅ローンを組んでいない、子供に安定した収入がある等が条件となってきます。
- Q. 親子間売買をする際の売買価格は?
- A. 親子間売買を行うからと言って価格を自由に設定できるわけではありません。債権者は市場価格での売買を希望しますし、親子間での売買を認めない金融機関もあります。
⇒解決できない疑問点はフリーダイヤル(
0120-963-281)か
無料相談フォーム、または
公式LINEアカウントよりご相談ください。専門家が回答いたします。
当協会の親子間売買について
親子間売買は慣れていない不動産会社が行うと成功の確率が大きく下がります。
一方当協会はこれまで多くの親子間売買を成功に導いてきました。ご自宅だけで親子間売買を進めると失敗し、断られた履歴が個人情報として半年間残りその後も断られる可能性が増えるため、そうなる前に一度ご相談ください。当協会のリースバック専門スタッフがご対応させていただきます。フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は
無料相談フォーム、または
公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
親子間売買やリースバックが出来た成功事例
親子間売買は住宅ローンの問題の他に、債権者への説得など、多くの調整を要します。そのため、
豊富な経験と確かなノウハウが必要不可欠です。ここでは、当協会が行った親子間売買や親族間売買、そして投資家が購入しリースバックした解決事例をご紹介しています。
-
相談内容:
ご相談者Eさんは大手の会社にて役員として勤務されていました。自宅はご自身夫婦とお父様・お母様と一緒に暮らされていました。仕事も順調で今までは問題な…詳細の成功事例
-
相談内容:
娘さん二人から親の家を買い取るにはと相談頂きました。75歳になる高齢な父親の事業が立ち行かなくなたため会社・個人とも債務整理を行いたい。父⇒娘の売…詳細の成功事例
-
相談内容:
自営業を営んでいるMさん。事業開始時に運用資金を捻出するためにお住まいを担保に融資を受け、やりくりをしてこられました。しかし、年々支払い条件などが…詳細の成功事例
親子間売買の成功事例一覧
親族間売買が出来た成功事例
-
相談内容:
会社経営をしていたAさんは、事業破綻により総額約5000万円の負債を抱えてしまい、会社倒産によって会社は清算済み。ご自身は個人再生を検討し、約3年…詳細の成功事例
-
相談内容:
相談者のIさんは、離婚をされる事になり、お子様とご自身とで現在のマンションに継続して住み続けたいとのご希望がありました。しかし、マンションの名義は…詳細の成功事例
-
相談内容:
東京都中野区のAさんから兄弟間の不動産売買、住宅ローン借り換えのご相談です。Aさん奥様のご実家の物件に関してご相談で、内容は土地は義母の所有、建物…詳細の成功事例
親族間売買の成功事例一覧
親子間売買・親族間売買に関する無料メール相談
このページの先頭へ▲

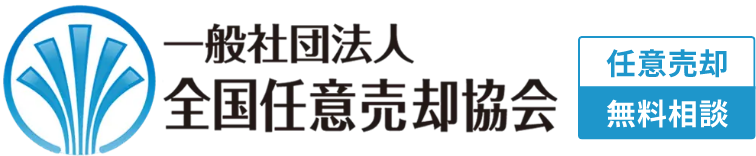
 LINE相談
LINE相談
 メール相談
メール相談
 無料相談予約
無料相談予約